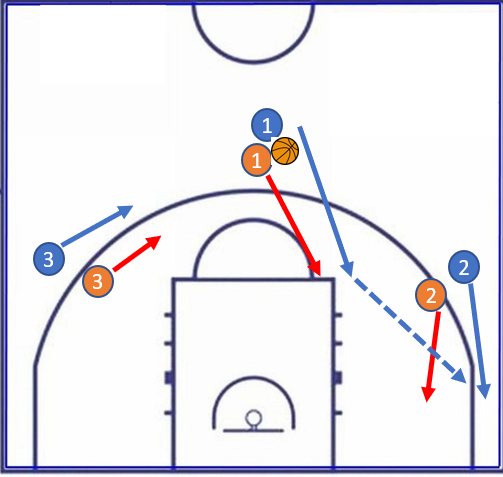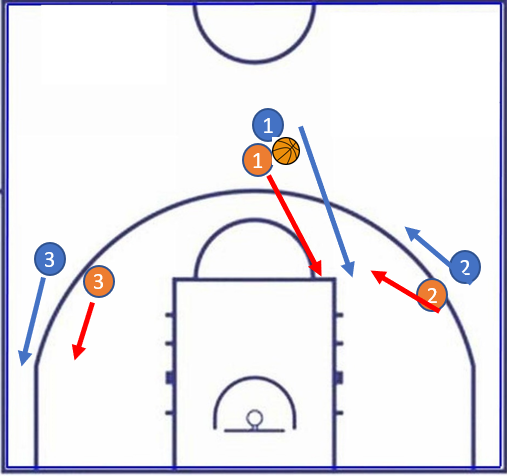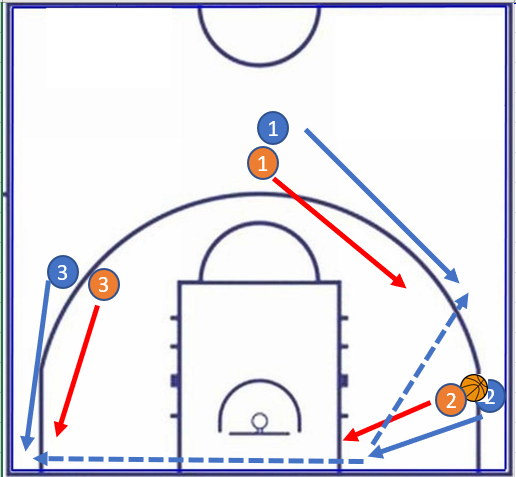【バスケセンスとは】
「バスケセンスが身につく88の発想 レブロン、カリー、ハーデンは知っている(著者:小谷究、網野友雄)」では、バスケセンスを「バスケに関わる状況を判断し、適切な方法を発想し実行できる力」と定義しています。
感覚的(センス)な主観と、論理的な客観を結びつける感性工学によれば、「センスは情報量に比例する」そうです。
つまり、センスとは先天的(持って生まれた才能)な資質ではなく、後天的(育ってきた環境)に磨いていく要素となります。
【バスケセンスを磨くには】
バスケセンスを磨くには、シャワーのようにバスケの情報を浴びることが必要となります。
特に高品質、最先端の情報を積極的にインプットすること。
書籍でも、研修でも、トレーニングキャンプでもいいので、自ら情報を広げに行くこと。
インターネットだけでも、色々な動画・技術・知識を取得することが可能です。
今まで培っていた常識はスクラップ&ビルドしてください。
そして、インプットした情報をどんどんアウトプットすること。
「知識(インプット)と行動(アウトプット)は成功の為の両輪、どちらか一つでは前に進めない」という言葉があります。
どんなに有益な情報を大量に取得したとしても、実際に試してみないと、自分に合うのか?チームに合うのか?は分かりません。
アウトプット時に注意してほしいのは、時間がかかるということです。
ほとんどのことがすぐには自分の物にはならず、今までのやり方がやりやすく感じ、自分の技術として取り入れるのはなかなか難しいです。
何度も練習でアウトプットして、試合でも使って、自分の技術にしてみてください。
「1、今までの常識」と、「2、常識にとらわれないセンスのある発想」に対比する形で様々なプレイを紹介したいと思います。
今回は、冒頭でも紹介した書籍「バスケセンスが身につく88の発想」で扱われているテーマを中心に紹介していますが、内容や結論は個人的な意見ですので、書籍の見解とは異なっていることが多いです。
【ポジションごとに役割を分担する?】
参考:バスケセンスが身につく88の発想、P26ポジションレス
バスケットボールはポジションごとに明確な役割分担があります。
PGはボールを運び、ゲームメイクする。
SGは3Pを中心に点を取る。
SFは得点を中心にオールラウンドに活躍する
PFはリバウンドを取ってハイポスト付近でプレイする。
Cはディフェンスの要(リムプロテクター)となり、ローポスト付近でプレイをする。

〇ストレッチ4
ストレッチ4とはインサイド付近でプレイしていた4番プレイヤーがアウトサイドに広がる(ストレッチ)ことです。
最近ではストレッチ4(アウトサイドでプレイするPF)どころか、ストレッチ5まで登場しました。
4番5番ポジションが3Pシュートを身に付けたおかげで、アウトサイドに広がり、ファイブアウトの形が可能となりました。
ストレッチ4のおかげでGやFが積極的にペネトレイトできるようになりました。…