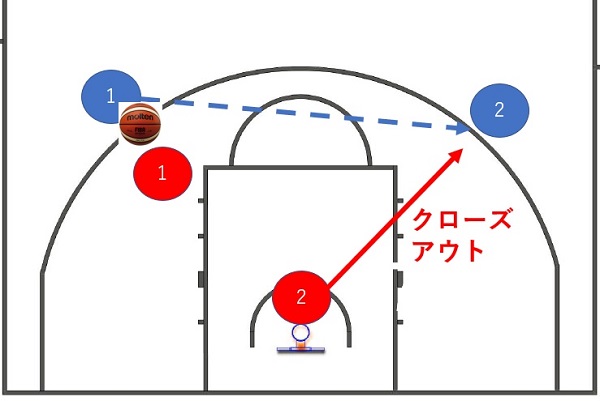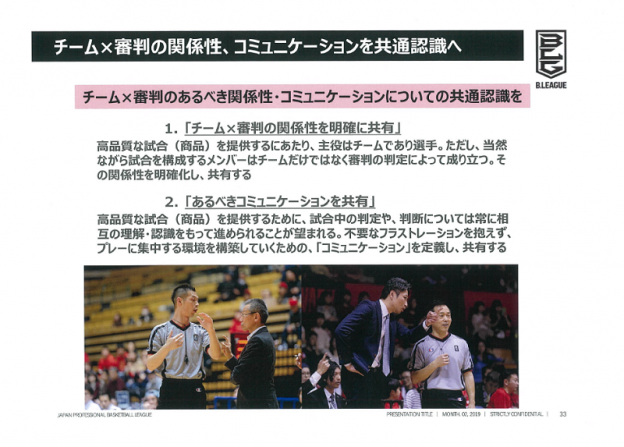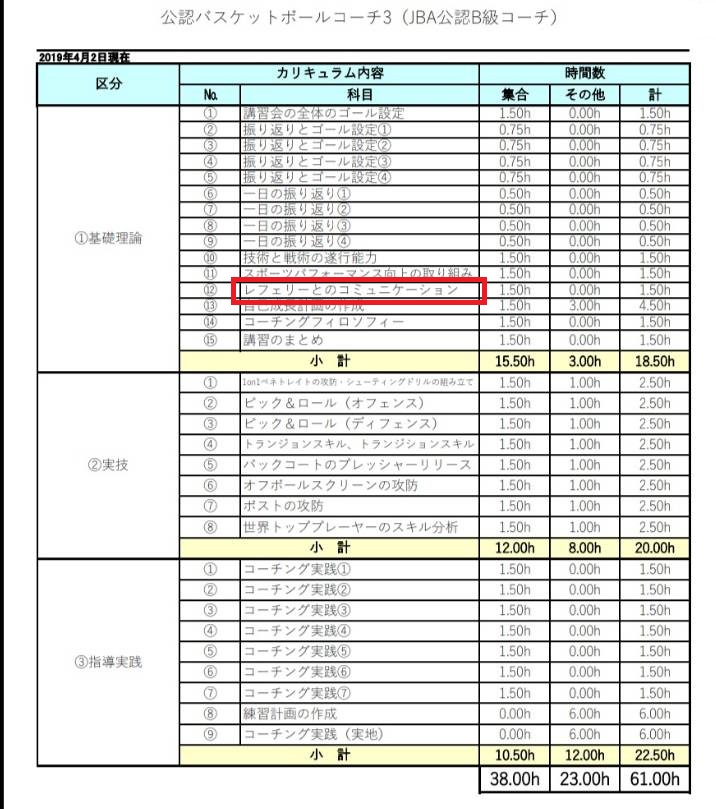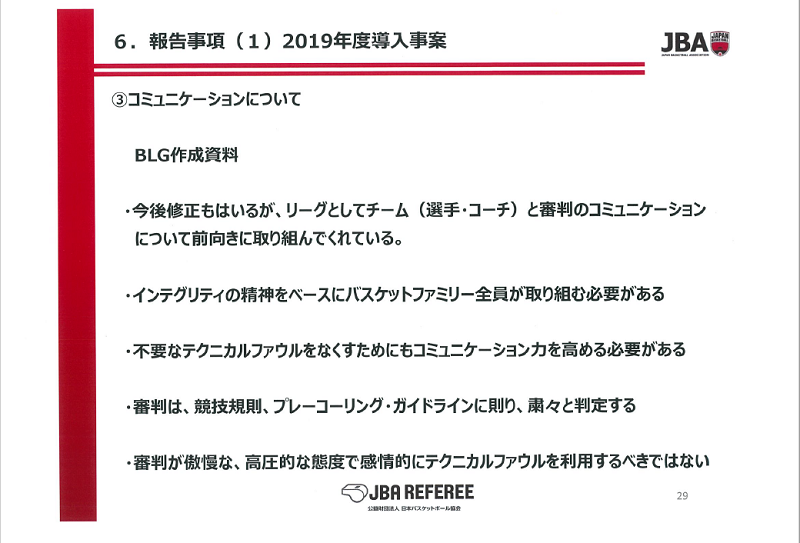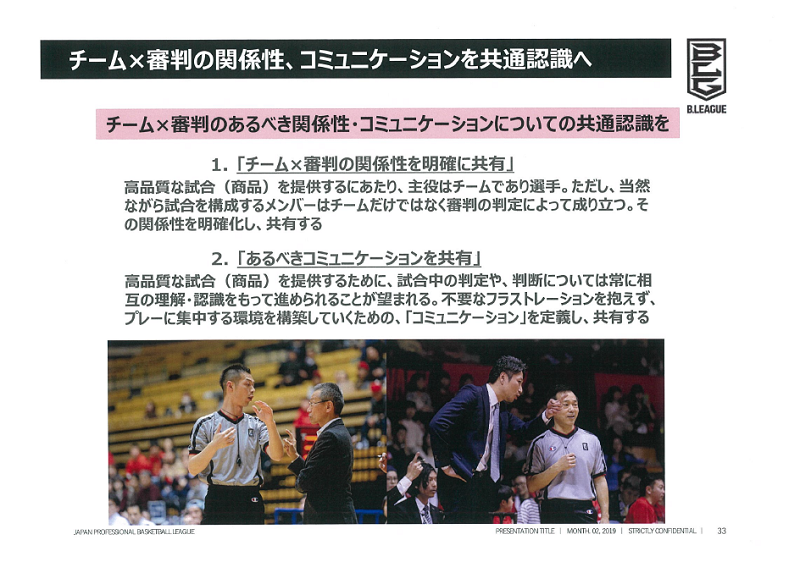「奇跡のレッスン〜世界の最強コーチと子どもたち〜バスケットボール編」というテレビ番組がやっていました。
内容は、三年生が引退し、新しく自分たちの代となった公立の中学校に、160cmの元NBAプレイヤーであるマグジー・ボーグスが7日間、コーチとして指導する内容でした。
短期的なコーチなので、主な指導内容はマインドセットでした。
自信の持てない中学生に自信をつけさせて、最後は強豪チームとの練習試合で接戦にまで持ち込むことができました。
その番組で出てきた言葉で強烈に印象に残ったのが「セカンドネイチャー」でした。
【セカンドネイチャー】
セカンドネイチャーとは、直訳すると第二の本能です。
第一の本能とは、生まれつき持っている能力や習性のことで、生命に対する防衛反応などです。
危ないと思ったら、頭を守って、身をかがんだりします。
そんな練習をする人はなかなかいないと思いますが、本能的にできてしまいます。
第一の本能に対して第二の本能とは、経験から後天的に身についた能力や習性を指します。
例えば、練習で一度もレイアップをしたことも見たこともない人は、いきなり試合でレイアップをうつことはありません。
練習でレイアップを繰り返すので、試合で、何も考えなくてもレイアップすることができます。
何も考えなくても、反復練習の結果、体が自然に動くことをセカンドネイチャーと呼びます。
【無意識を有意識に、有意識を無意識に】
「無意識を有意識に」とは、普段何気になくやっている行動や習慣を、意識して(頭を使って)やるようにすることです。
「有意識を無意識に」とは、何度も意識的に反復することで、セカンドネイチャーに落としこむことです。
〇無意識・無能
「知らない(やらない)・できない」状態です。
今、自分ができるプレイ以外をやらずに、無自覚で成長を求めていません。
「インサイドプレイヤーだから3Pは必要ない、練習しない」状態です。
〇有意識・無能
「知っている(やっている)・できない」状態です。
意識的に取り組んでいますが、始めたばかりなので当然うまくいきません。
うまくいかないと苦痛なので、継続的に取り組めず、三日坊主になってしまいます。
そして考えながら行動するという動作は不快なので、余計にやりたくなくなります。
「インサイドプレイヤーだけど3Pを練習しているが、入らないのでつまらない」状態です。
〇有意識・有能
「知っているし、意識したらやっている・できる」状態です。
継続的に正しく練習すれば、だれでも上達します。
うまくなったという成長を自覚できれば、より継続できます。
しかし、成長を続けても停滞期は訪れます。
この停滞期を機に、これ以上やってもうまくならないと勘違いをして断念する可能性もあります。
まだ有意識として頭を使って行動しているので、快適ではありません。
「インサイドプレイヤーだけど3Pが少し入る、考えながらシュートしている」状態です。
〇無意識・有能
「知っているし、意識しなくてもやっている・できている」状態です。
反復練習のおかげで、技術がセカンドネイチャーにステップアップしました。
有意識の状態を脱すると、無意識の動作が可能なので、オンザコートでは最速に適切な判断ができます。
頭を使う必要もないので、快適にプレイができます。…