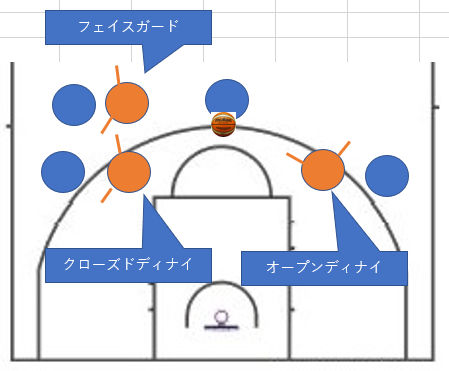【ドリブルとは】
ドリブル (Dribble) とは、ボールを保持しているプレーヤーが、ボールを連続して床に弾ませながらコート上を移動する手段のことです。

【ドリブルの三要素】
ドリブルで相手を抜くためにはスピード×パワーの要素に、テクニックを足した3つの要素で考えています。
・スピード
ボールを前に進めるスピードです。
スピードが速ければ、相手を容易に抜き去ることができます。
ドリブルにおいて、もっとも必要な能力です。
・パワー
当たり負けしないフィジカルです。
フィジカルで負けてしまうと、ボールが抜けても体が抜けません。
また、スピードで負けていても、パワーで圧倒していれば、トルソーに入られなければ、相手をはじきながら抜くことが可能となります。
・テクニック
ハンドリングの技術やバリエーションです。
スピード×パワーで多少劣っていても、テクニックで翻弄すれば、相手を抜くことが可能となります。
ベテランになれば身体能力が劣ってくるので、テクニックを向上させる必要があります。
【ドリブルを使用するシチュエーション】
ドリブルは、シチュエーションに合わせて、意図をもって意識的に行います。
どういったシーンに、どのようなドリブルをするかを解説します。
・ドライブ
レイアップのためのドリブルです。
ボールをロストしないようにスピードとパワーが大事です。
アタックドリブルとクラブドリブルの二種類あります。
・プレッシャーリリース
後方に下がったり、密集地帯などから抜けるたりするために使うドリブルのことです。
ターンオーバーを避けるために行うので、コントロール(テクニック)が大事となります。
・ボールプッシュ
ボールを素早くフロントコートに進める時のドリブルです。
なによりもスピードが優先されます。
以前はパスで進めた方がよいとされていましたが、最近ではドリブルでボールプッシュする方が良いという考えも増えてきました。
ボールプッシュでは、ドリブルの方がパスよりもターンオーバーの確率が低いからです。
単にボールをフロントコートに進める場合は、キャリーと呼びます。
・ボールキープ
セットプレイを組み立てる時など、一定時間ボールを取られないようにするドリブルのことです。
ディフェンスとしては抜かれる心配はないので、プレッシャーをかけやすくなります。
その分、ハンドラーは、ボールをキープするテクニックが大事となります。
・ボールダウン…