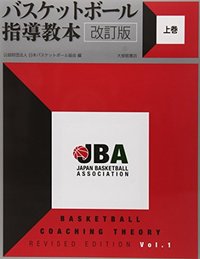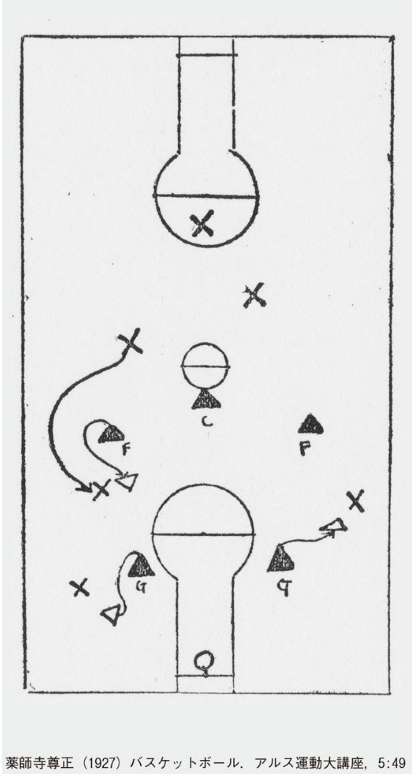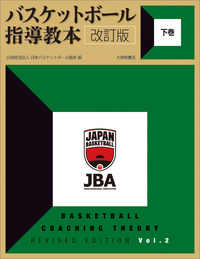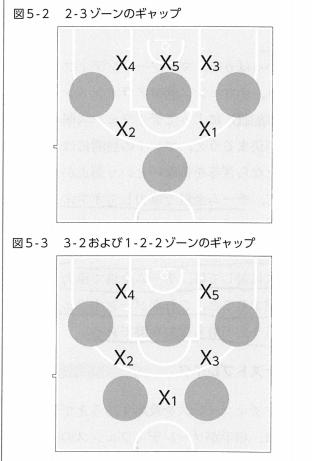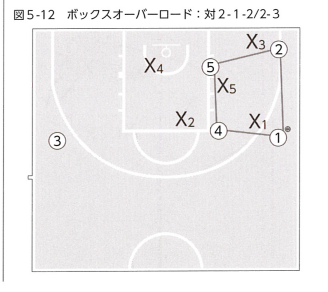今までに読んだバスケ専門書です。
主に自分への記録として紹介します。
カテゴリーや能力によって「マッチング率」は変わってくると思います。
私にとってマッチング率が高かった書籍だけAmazonのリンクを張っておきます。
【バスケセンスが身につく88の発想 レブロン、カリー、ハーデンは知っている(2019/4/24)】
著者:小谷究、網野友雄
「レブロン、カリー、ハーデン」というタイトルが、ファッション性を意識してしまい、逆に私を遠ざけていました。
しかし、呼んでみると面白い内容でした。
従来は良しとされている常識以外にも、様々な選択肢を提案してくれます。
従来の常識という最低限のバスケIQがないと、伝わりにくいかもしれません。
【100問の“実戦ドリル”でバスケiQが高まる(2018/12/3)
著者:小谷究、 佐々木クリス
「バスケ版の詰め将棋」という触れ込みでしたが、違和感が大きいですね。
バスケは、全く同じ状況でもプレイヤーや対戦相手、残り時間や点差によって判断がかわるので、しっくりは来なかったですね。
【バスケットボールの戦い方 [ピック&ロールの視野と状況判断](2018/9/4)
著者:佐々宜央
■序 章:ピック&ロール戦術について
■第1章:ドライブ&リアクトの導入
■第2章:ピック&ロール(サイド)
■第3章:ピック&ロール(サイド)
■第4章:ピック&ロール(エルボー)
■第5章:ピック&ロール(トップ)
書籍での3Dは見ごたえはありました。
クラブチームではピックプレイをここまで細分化されていないので、実践はできませんでした。
【バスケットボール 判断力を高めるトレーニングブック(2018/9/4)
著者:鈴木良和、森高大
■第1章:バスケットボールにおける判断力とは――
■第2章:判断力を磨くトレーニング
■第3章:オンボールスクリーンの認知・判断・実行
■第4章:ディフェンスの工夫を上回る
【バスケットボール 勝つためのディフェンスの教科書(2018/9/3)
著者:倉石平、田渡優
■PART1:ディフェンスのセオリー
■PART2:ディフェンスの種類と特徴…