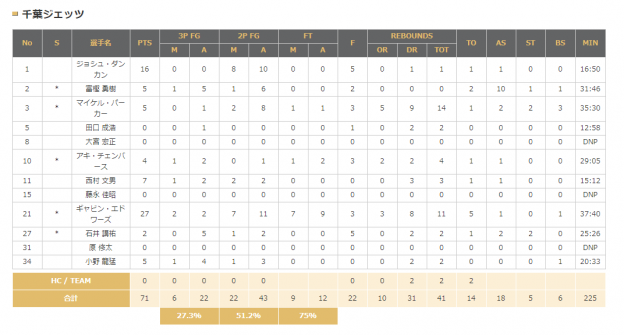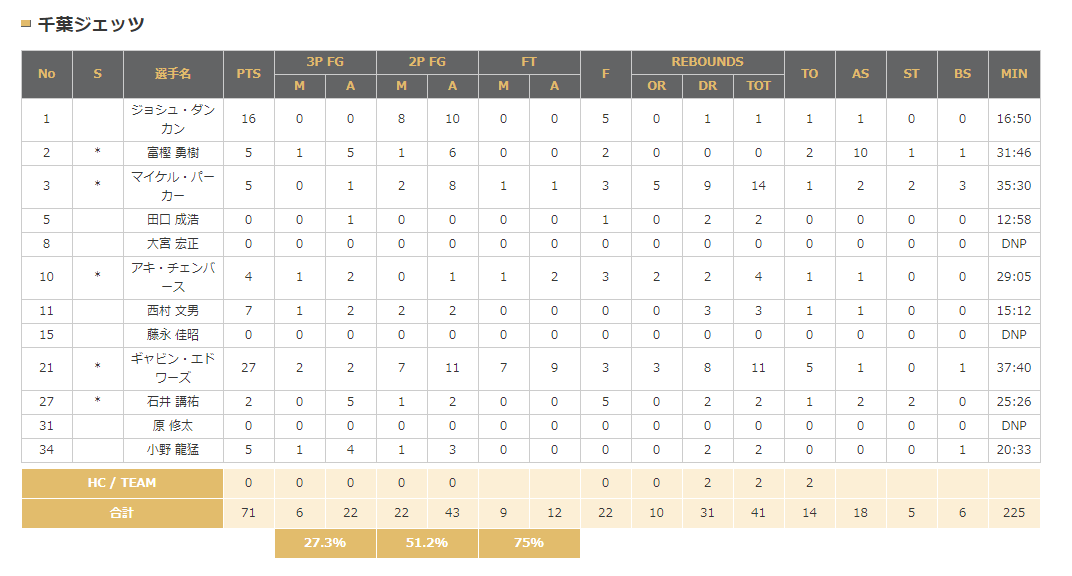ターンオーバー考察(2016.08.09)という記事がありますが、
6年も経ったので、自チームに特化して再考察したいと思います。
【ターンオーバーのデーター&目標】
当チームのターンオーバー目標は10個/試合(8分ゲームなら8個)です。
ハーフで5個、クォーターで2.5個、4分で1個の計算となります。
GOEMONのデータ上は下記となっております。
10.0個/目標
17.1個/全試合
16.5個/直近25試合
14.2個/Wリーグ平均
16.5個を10個にするためには約40%削減する必要があります。
ハドルのおかげでターンオーバーの映像が手に入ったので、確認できた337個を分類化してみました。
【ターンオーバーの分類化】
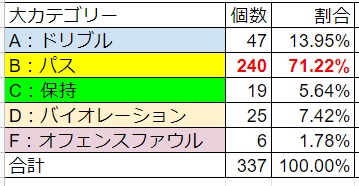
合計:337個(100.00%)
A、ドリブル:47個(13.95%)
B、パス:240個(71.22%)
C、保持:19個(5.64%)
D、バイオレーション:25個(7.42%)
F、オフェンスファウル:6個(1.78%)
3回に2回以上はパスのターンオーバーだと思っていたので、大体想定通りの割合でした。
その他の項目で言えば、オフェンスファウルが少なすぎます。
25試合に対して6個しかないのは、グレーゾーンを攻めなさすぎですね。
オフェンスファウルは、1試合に1個は欲しいと思います。
話を戻して、40%削減するとなると、やはりパスの改善が必要となります。
【なぜパスのターンオーバーが多いか?】
完全な主観ですが、パスのターンオーバーが多い理由は下記と想像しております。
1、パッサーのスキル
2、レシーバーのスキル
3、パッサーとレシーバーのコミュニケーション
例えば、ドリブルであればドリブラーのスキルという項目になります。
対してパスは上記の3つのスキルが必要となり、単純にドリブルの3倍のリスクが顕在すると考えています。
あとは単純にアウトサイドからペイントにボールをタッチさせるのが、ドリブルよりもパスの方が圧倒的に割合が多い(つまりチャレンジの分母がパスの方が多い)のも理由だとは思います。
【ターンオーバーの小分類化】
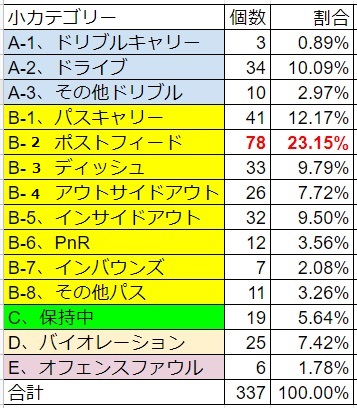
さらに細かく分類化しました。
A-1、ドリブルキャリー:フロントコートまで運ぶドリブルミス。
A-2、ドライブ:アウトサイドからペイントに向かうドリブルミス。
A-3、その他ドリブル:リトリート(下がる)や、キープなどのドリブルミス。
B-1、パスキャリー:フロントコートまで運ぶパスミス。
B-2、ポストフィード:ボールをポストアップしているインサイドにいれるパスミス(アウトサイド・イン)。…